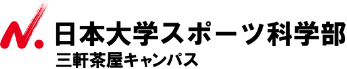平成30年度後学期 第3回公開講座の開催報告
| 開催日時 | 12月12日(水)13時~14時30分 |
|---|---|
| 表題 | 「スポーツのタレント(才能)とは」 |
| 講師 | スポーツ科学部教授 森丘保典 |
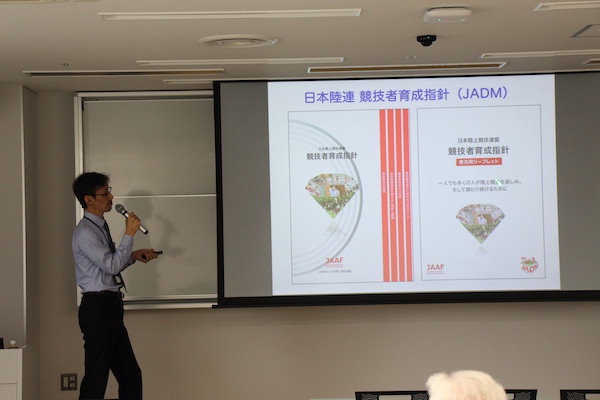
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定して以来、以前にも増して指導者や保護者の過熱による子ども達の身体的、心理的な負担の増加が懸念されている。本講座では、若年期アスリートの育成・強化に関する近年の国内外の考え方や具体的な取り組みについて紹介ながら、望ましい子どものスポーツ活動のあり方について展望した。
まず、日本陸上競技連盟における日本代表選手の調査等から得られたエビデンスを踏まえて、「小中学校期は、競技成績が著しく発達する傾向にあるが、この時期の競技成績の優劣には発育発達の遅速が大きく影響すること」、「日本代表の約6割は中学校期に全国大会に出場しておらず、多くの選手が競技間・種目間トランスファーを経験していること」、「世界トップレベル競技者の多くは、日本代表よりも自己ベスト記録に至る年齢が高く、維持する期間も長い傾向にあること」などを示した。そして、ジュニア期の競技成績の優劣には発育発達の遅速(早熟型や晩熟型)が大きく影響するとともに、シニア期まで様々な工夫や努力を重ねながら競技を継続していかなければ日本代表レベルで活躍することはできないことを踏まえて、最大のスポーツ適性は、人間に行動を起こさせ、それを継続へと向かわせるための「動機づけ」であるともいえることを示唆した。
以上のことから、子どものスポーツに関係する大人達には、「早生まれの選手たちを含む“晩熟型”のドロップアウトはもとより、早期に高いレベルに到達した“早熟型”の選手たちのバーンアウトにも十分に配慮する必要があること」、「特に小中学校期の競技成績による将来性の評価や選抜には慎重を期す必要があるとともに、多様な競技や種目を経験しながら高校期以降で最適種目を決定していくプロセスが重要であること」などを強く認識する必要があることを確認した。
まず、日本陸上競技連盟における日本代表選手の調査等から得られたエビデンスを踏まえて、「小中学校期は、競技成績が著しく発達する傾向にあるが、この時期の競技成績の優劣には発育発達の遅速が大きく影響すること」、「日本代表の約6割は中学校期に全国大会に出場しておらず、多くの選手が競技間・種目間トランスファーを経験していること」、「世界トップレベル競技者の多くは、日本代表よりも自己ベスト記録に至る年齢が高く、維持する期間も長い傾向にあること」などを示した。そして、ジュニア期の競技成績の優劣には発育発達の遅速(早熟型や晩熟型)が大きく影響するとともに、シニア期まで様々な工夫や努力を重ねながら競技を継続していかなければ日本代表レベルで活躍することはできないことを踏まえて、最大のスポーツ適性は、人間に行動を起こさせ、それを継続へと向かわせるための「動機づけ」であるともいえることを示唆した。
以上のことから、子どものスポーツに関係する大人達には、「早生まれの選手たちを含む“晩熟型”のドロップアウトはもとより、早期に高いレベルに到達した“早熟型”の選手たちのバーンアウトにも十分に配慮する必要があること」、「特に小中学校期の競技成績による将来性の評価や選抜には慎重を期す必要があるとともに、多様な競技や種目を経験しながら高校期以降で最適種目を決定していくプロセスが重要であること」などを強く認識する必要があることを確認した。